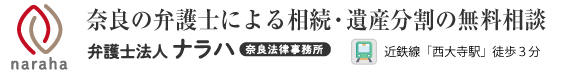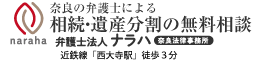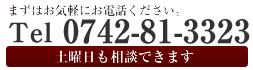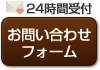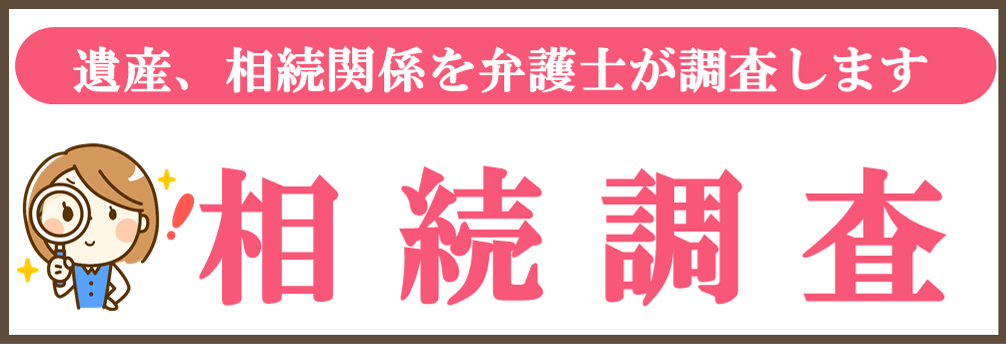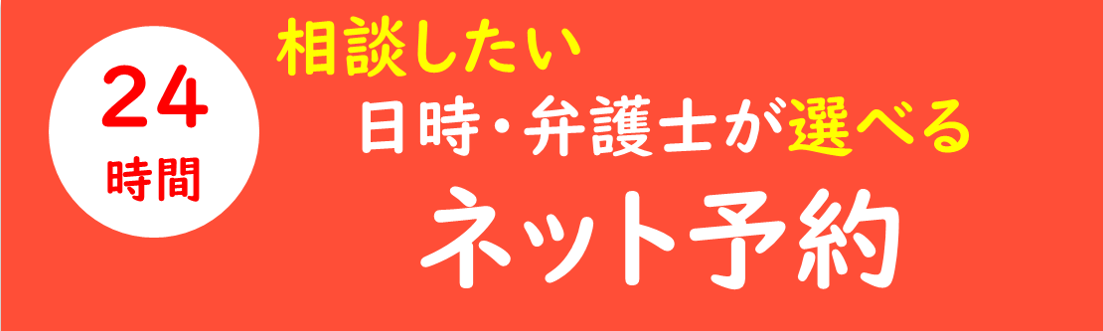生前対策(遺言作成)を行いたい
生前対策として、遺言を作成したいとき、作成すべきは、公正証書遺言です。
その理由は、自筆証書遺言では、争いの種がありすぎるためです。
以下では、自筆証書遺言に生じうる難点をご説明します。これにより、専門家である弁護士に依頼して公正証書遺言を作成することの意義を感じていただけますと幸いです。
亡くなられた方が、遺言を書いていた
ご親族が亡くなられ、悲しみに暮れていたところ、突然、寝耳に水の話が飛び込んでくることがあります。
「いつの間に、このようなものを書いていたのか…」
存在を全く知らなかった遺言が出てきたとき、これは、本当に、亡くなった人物(遺言者)の意思を示したものなのかと不安になり、疑念を抱くこともあるでしょう。
「なぜ、遺産のすべてを彼に渡すのか、分からない」
「相続人である私が、遺産をこれだけしかもらえないのは、どうしてなのか」
遺言が、遺言者の意思にしたがって作成されていないかもしれないと考えた場合、遺言の無効を主張することが考えられます。
もし遺言が無効であるということになれば、他に有効な遺言がない限り、遺産の分け方については、相続人間での遺産分割協議の中で話し合うことになります。
では、遺言はどういう場合に無効となりうるのでしょうか。
遺言にはいくつか種類があります。しかし、よく問題になるのは、自筆証書遺言です。
1 自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が、自筆で、単独で作成することができます。
このように、自筆証書遺言は、比較的容易に作成できるものですが、それゆえに、内容、作成方法や作成状況などの点で疑義が生じることも少なくありません。具体的には以下の事情がある場合には、遺言は無効となることがあります。
2 遺言が無効となりうる場合
(1)遺言の内容が、不完全である
法律上認められていない事項が書かれている、また、内容が不確定、確定不能な場合、遺言は無効となります。
遺言の解釈は、文言を形式的に判断するだけではなく、様々な要素を総合的に考慮して行われます。遺言者の意思を尊重し、可能な限り遺言が有効になるような解釈をすることが遺言者の意思に沿うものであると考えられてはいるのですが、遺言者の意思を探求した結果として、有効な内容と確定できない場合には、遺言は無効とならざるを得ません。
(2)遺言の書き方、方式に不備がある
今日、自筆証書遺言は、相続財産の目録を除き、遺言のすべての部分を自筆で書く必要があります。ワープロによる印字や他人の代筆は、それが一部であっても許されず、遺言は無効となります。
また、自筆で書けていたとしても、気をつけなければならないことがあります。例えば、日付については、年月の記載はあるが日の記載がないときは、遺言は無効となります。
(3)遺言者が、遺言内容の理解や判断をすることができなかった
遺言は、作成当時に、遺言者に遺言能力があったことが求められます。遺言者が、遺言の内容を理解していない、遺言について判断することができなかった場合は、遺言は無効となります。
遺言の有効性に関して、こういった点が問題になりうるのは、遺言が遺言者の意思に基づき作成されているとは限らず、遺言者の近くにいる者の意思が関与し、遺産独占などの手段として利用されていることがまま見られるからであるといえます。
(4)遺言が、偽造された
知らない間に遺言が作成されていた、遺言の内容が不自然で納得がいかないなど、遺言者(とされる人物)とは別の人物が遺言を作成したのではないかとの疑念が生じるとき、遺言が偽造された可能性を考えます。
偽造を証明するために有用なものとして、筆跡鑑定があります。しかし、仮に、遺言の筆跡と対照資料の筆跡が、同一人によるものではないとの筆跡鑑定結果が得られたとしても、それだけで遺言が偽造されたと判断されるわけではなく、他の諸事情も踏まえたうえで、総合的に判断されます。
遺言に関するご相談は当事務所まで
今回は、遺言の中でも、自筆証書遺言を取り上げて、遺言が無効となりうる場合についてご説明致しました。
自筆証書遺言は、その簡便さの反面、後にトラブルが起きやすいところ、第三者で公務員の立場にある公証人が作成に関与する公正証書遺言は、トラブルが比較的少ないといえます。
当事務所では、遺言を作成しておくことで、事後のトラブルをできる限り減らしたいとの思いもあり、公正証書遺言作成の依頼をお受けしております。上述の点に留意し、あとから無効と主張されないように遺言を作成することを大事にしています。当然のことですが、遺言を作成する際には、遺言者の意思を尊重致します。
遺言に関するご相談は、ぜひ、当事務所の弁護士まで、ご連絡ください。
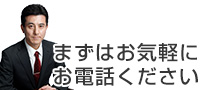
ください
【電話受付時間】
平日9:00~17:00
事務所案内
 弁護士法人 ナラハ奈良法律事務所
弁護士法人 ナラハ奈良法律事務所〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
サイト内検索
当事務所の関連サイト
ご利用方法
1 相談のご予約
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
0742-81-3323
相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
2 弁護士による法律相談
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
3 ご依頼
相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
住所
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
電車
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
自動車
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。