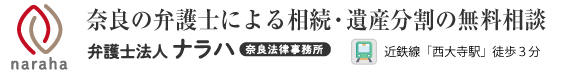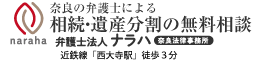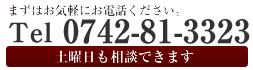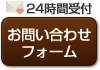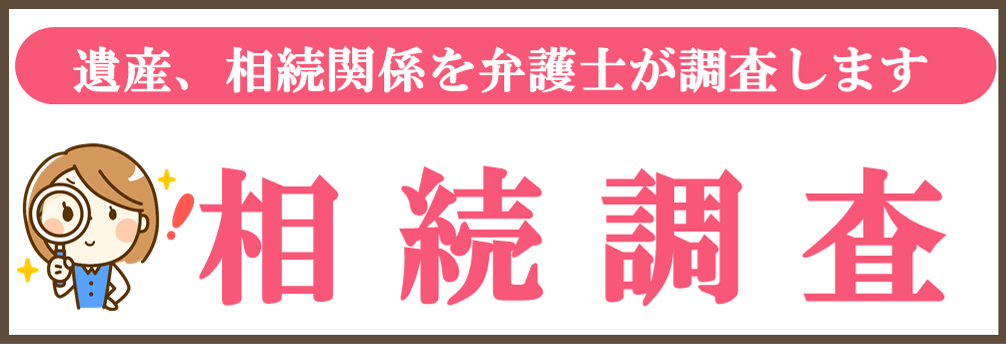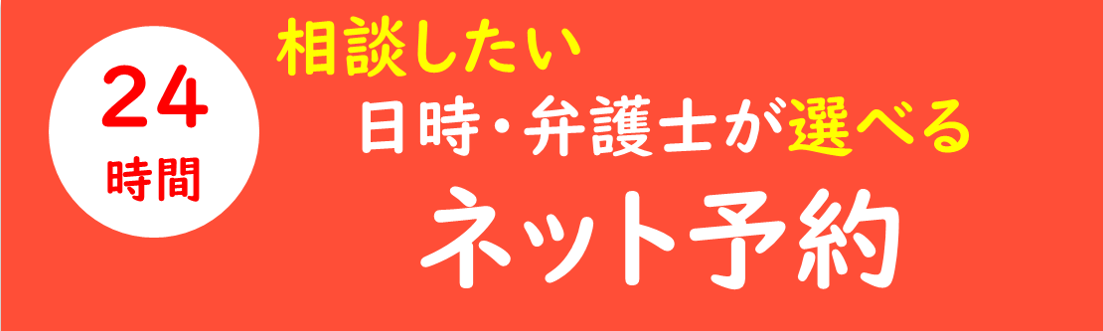特別受益について
1 特別受益(とくべつじゅえき)が問題になる場合
法定相続人の中に、被相続人から遺贈や生計の資本のために多額の生前贈与を受けていた人がいた場合、その贈与などで受け取った利益のことを「特別受益」といいます。
贈与が「特別受益」となった場合、遺産分割において、その「特別受益」を相続財産に加算して、具体的な相続分を算定することになります(下記3の「特別受益の持戻し」をご覧ください)。
遺産分割協議や調停において争われるのは、どのような贈与が「特別受益」に該当するかです。よく争いになる費用について、一般的な文献では、次のように整理されていますが、ケース・バイ・ケースです。
| ①住宅ローンの頭金 | 原則として、特別受益となる。 |
|---|---|
| ②結婚式の費用 | 原則として、特別受益とならない。 |
| ③生活費の援助 | 原則として、特別受益とならない。 ただし、親族間の扶養の範囲を超えるといえるものは、該当することがある。 |
| ④大学進学費用 | 原則として、特別受益とならない。 ただし、私立大学医学部の入学金は該当することがある。 |
| ⑤生命保険金 | 原則として、特別受益とならない。 ただし、著しい不公平が生じるような特段の事情がある場合は、該当することがある。 |
「特別受益」という制度の目的は、いわば「遺産の前渡し」といえるような趣旨の贈与等があった場合に、相続人間の公平を保つことが目的です。「遺産の前渡し」とはいえない程度の贈与は、「特別受益」にはならないと考えられています。
2 特別受益を主張する流れ
特別受益は、遺産分割の話し合いの中で、テーマになります。「特別受益があったと主張する側」が、出来る限りの資料や証拠を集めて、特別受益を考慮した遺産分割を求めていくことになります。
(1)遺産分割協議―最初の切り出し方
たとえば、相続人同士で、
「あなたは、○○(贈与など特別受益の具体的内容)を受け取っているから、相続分は少なくていいのではないでしょうか。○○の金額を持ち戻して、計算しましょう」といった形で切り出されます。
話合いの中で、「特別受益」の有無と評価について合意が成立すれば、相続分を計算し直し、遺産分割の条件が決まります。
この場合、「遺産分割協議書」を作成します。
(2)調停・審判
相続人間で、「特別受益」について合意が成立しない場合、遺産分割協議の全体が成立しません。解決するためには、「調停」という手段があります。
調停では、家庭裁判所の調停委員を介して、話し合いを行います。
特別受益についても、具体的な証拠に基づいて、「特別受益」に該当するか、該当するとして金額的にどのように評価するのかについて、交渉が行われます。
調停をしても解決しない場合は、「審判」という手続きに移ります。審判では、証拠に基づいて、裁判所が判断を下します。
3 特別受益の持戻し
遺産分割においては、「特別受益」を相続財産に加算して、具体的な相続分を算定します。計算例をご説明するため、シンプルな例をご紹介します。
<事例>
| 法定相続人 | 配偶者A(法定相続分 2分の1) 長 女B(法定相続分 4分の1) 長 男C(法定相続分 4分の1) |
|---|---|
| 遺産 | 1億円 |
| 特別受益 | 長女Bに住宅ローンの頭金として2000万円を生前に贈与 |
①みなし相続財産の算定
まず、遺産を特別受益に加算し(持戻し計算)、みなし相続財産を算定します。
②一応の相続分の算定
次に、みなし相続財産に法定相続分をかけます(一応の相続分)。
Bの相続分 1億2000万円×(1/4)=3000万円
Cの相続分 1億2000万円×(1/4)=3000万円
③具体的相続分の算定
特別受益のあったBについては、特別受益の2000万円を控除します。各相続人の具体的相続分の合計は、遺産の額と一致します。
Bの相続分 1億2000万円×(1/4)-2000万円 =1000万円
Cの相続分 1億2000万円×(1/4)=3000万円
4 特別受益の持戻しの「免除」
被相続人は、意思表示によって特別受益者の受益分の持ち戻しを免除することができます。文書になっているものに限らず、黙示のものでも、免除の意思表示に該当するとされる余地はあります。
この点は、調停や審判においても、よく争われます。
ポイントは、「相続分以外に、財産を取得させる意思を有していたことを推認させる事情」があるかにありますが、ケース・バイ・ケースの判断となります。
詳しくは、弁護士に御相談ください。
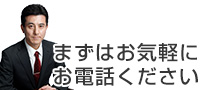
ください
【電話受付時間】
平日9:00~17:00
事務所案内
 弁護士法人 ナラハ奈良法律事務所
弁護士法人 ナラハ奈良法律事務所〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
サイト内検索
当事務所の関連サイト
ご利用方法
1 相談のご予約
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
0742-81-3323
相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
2 弁護士による法律相談
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
3 ご依頼
相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
住所
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
電車
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
自動車
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。