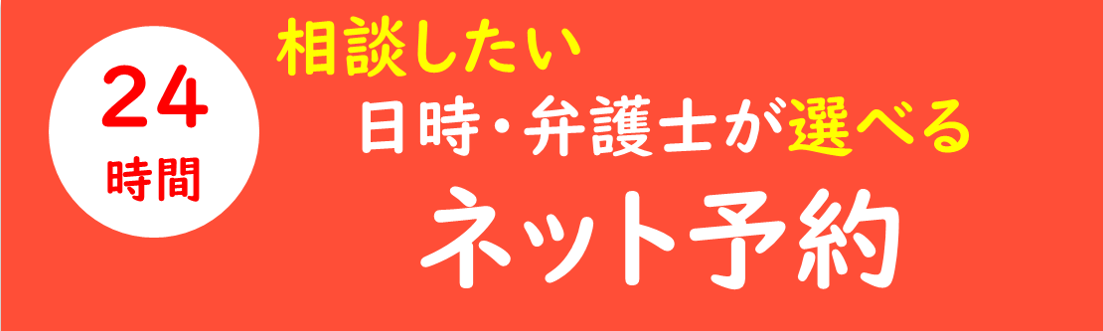親の生活費での使用は預貯金の使い込みになりますか?
- 2025年01月10日
- よくあるご質問
1 はじめに
(1)父や母が亡くなった後、相続の話合いがなされることと思います。
例として、子ども2人(AとBと言います。)が相続人である場合を考えます。Aが親の近くに住み、日常的に、親の預貯金を引き出していました。Bが、親の預貯金通帳を見て、これらの引出しについてAに問いただしたのに対し、Aが「これは、親の生活費で使用した」と言ったとします。Bとしては、Aが親の預貯金を使い込んだのではないかと考えているのですが、Aによる引出し(と、Aの主張では親のための使用)は、預貯金の使い込みと言えるのでしょうか。
(2)まず、前提として、親の預貯金の引出しの事実を知り驚いた相続人が取れる解決方法は何でしょうか。
まずは、相続人間で話し合い、それが親の生活費で使用されたと皆が納得すれば、残された預貯金についてどのように分けるかを話し合うのみとなります。他方で、親の生活費などではなく、引き出した相続人が自分のために使ったと認め、これをすでに受け取った分と見なして相続財産を計算することに同意するのであれば、そのとおり計算して遺産分割を行うということもあるでしょう。ここで問題となるのは、親の生活費といえるか、相続人間の意見に違いが生じる場合です。以下では、一つの考え方を示させていただきますので、これに基づき、親の生活費で使用したか否か、相続人全員で合意が得られた場合には、上記各方法によって遺産分割を行っていただくのでよいと考えます。
なお、合意に至らなかった場合には、下記のとおり留意点があります。合意できない場合、家庭裁判所における遺産分割調停や審判手続の利用を考えると思われますが、親名義の預貯金の引出しについては、実務上、遺産分割の対象外とされています。したがって、上記問題については、遺産分割調停や審判の中では解決が図れません。そこで、解決したいと考える相続人(B)は、預貯金を引き出した(と考えられる)他の相続人(A)に対し、不法行為に基づく損害賠償請求、又は、不当利得に基づく利得返還請求をするしかありません。
2 親の生活費といえるか否か、使い込みといえるか否か
(1)引き出した預貯金の使途は、引き出したAが一番よく知っているはずです。したがって、原則として、Aは、Bに対し、詳細な説明をすることが求められるでしょう。詳細な説明と言えるためには、預貯金の使途に関する客観的な資料を示すことも重要です。
(2)では、親の生活費と言えるか、使い込みといえるか否かに関する基準として、どのようなものが考えられるでしょうか。
明確なルールはないものの、一つの基準としては、当該支出が、日常的かつそれほど高額にならないことが多い類のものといえるか、それとも、非日常的かつ高額のもの(例として、不動産の購入など)といえるかどうかであると考えられます。
前者については、領収証が全て残っていなければ使途不明金と扱うとまで厳格に考えるのではなく、Aにおいて一定の説明ができれば、使途の説明としては足りると考えることもできると思われます(そもそも、この種の支出について完全な形で客観的証拠を残しておくということは期待し難いことであるだけでなく、むしろ不自然と言えるかもしれません。)。後者については、まず、やはり領収証などの客観的資料による裏付けがなされない限り、使途不明と捉えられてもやむを得ないのではないかと思われます。その上で、客観的資料があったとしても、それが真に、親のために使用されたものであるか、より詳細な説明が必要になると考えられます。
(3)使い込みと指摘される場合に備えて
いずれにしても、説明をして納得を得るためには、客観的資料の存在が重要であることは明らかです。預貯金通帳の「摘要」欄に明確に印字されるものであればそれで足りますが、そうでなければ、領収証等の資料はしっかり残しておくことが求められます。使い込みではないかと指摘されたときは、これらの資料を示しながら、丁寧に説明を尽くすことが重要です。
加えて、例えばAのように、親の近くに住み、親の預貯金を預かり管理している立場の者は、日頃から、Bに対し、親の預貯金の使途について説明をしておくことが望ましいと言えます。他方で、Bの側から見ますと、Aが親の預貯金の管理をしてくれているということに思いを馳せ、逐一の報告を求めることまではしないという選択肢も検討してみるなど、円満な将来の相続に備えることも大切だと思います。
3 それでも、もめてしまったときは弁護士に
親の生活費で使用したと言えるか、使い込みと言えるか否かについては以上のとおりです。 気を付けていただくことが第一ですが、それでも、もめ事になってしまうことは、どうしてもあります。
そのような場合は、ぜひ、相続に詳しい、ナラハの弁護士までご相談いただければと思います。
使い込みであるとの指摘の仕方、使い込みであると指摘された場合の対応方法について、できることとできないことを明確にしてご説明、アドバイスさせていただきます。
相続に関するご相談は、初回60分無料でご案内しております。どうぞ、お気軽にご相談ください。
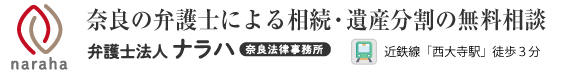
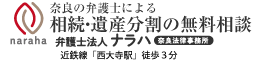

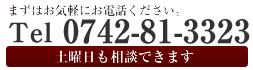
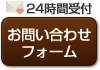

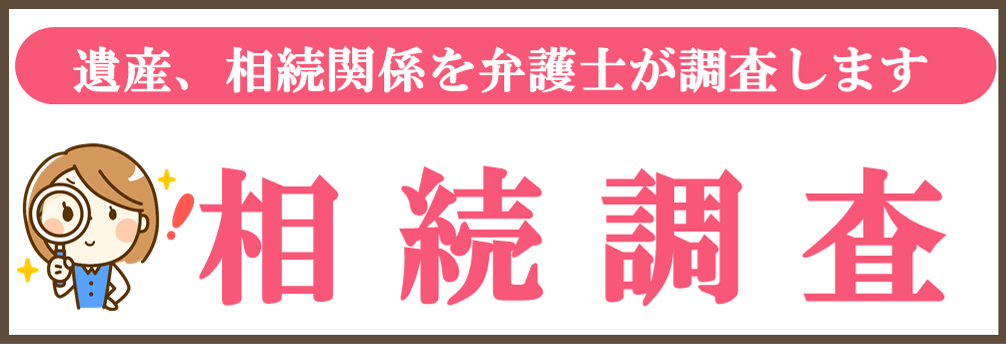

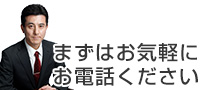

 弁護士法人 ナラハ奈良法律事務所
弁護士法人 ナラハ奈良法律事務所