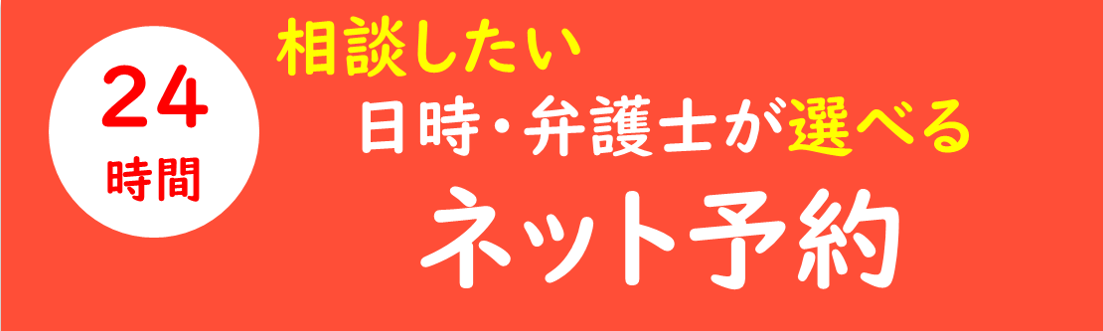2023年12月13日から,改正空家対策特別措置法が施行されています。
- 2024年01月8日
- 最新情報・お知らせ
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が,令和5年12月13日に施行されました。空き家等の活用拡大,管理の確保,特定空家対策に総合的に取り組みための法律です。
改正法の概要は次のとおりです。
(1) 所有者の責務の強化
現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を追加
(2) 空家等の活用拡大
(3) 空家等の管理の確保
市区町村長は,放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として,指 導・ 勧告。 勧告を受けた管理不全空家等の敷地は,固定資産税の住宅用地特例が解除となる。
従来は「特定空家等」のみが対象だった固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)の解除が、改正法では「管理不全空家等」も対象になることが組み込まれました。これにより,現在は特定空家等に指定されていなくても,放置すればその可能性があると判断されれば,管理不全空家等として,固定資産税の住宅用地特例が解除され,固定資産税がこれまでの6倍になってしまいます。
(4) 特定空家等の除却等
市区町村長に特定空家等の所有者等に対する報告徴収権を付与
特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度を創設
所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化
市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与
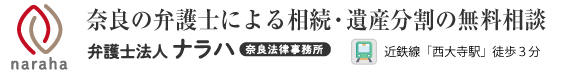
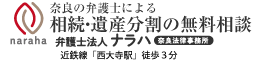

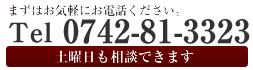
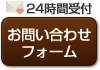

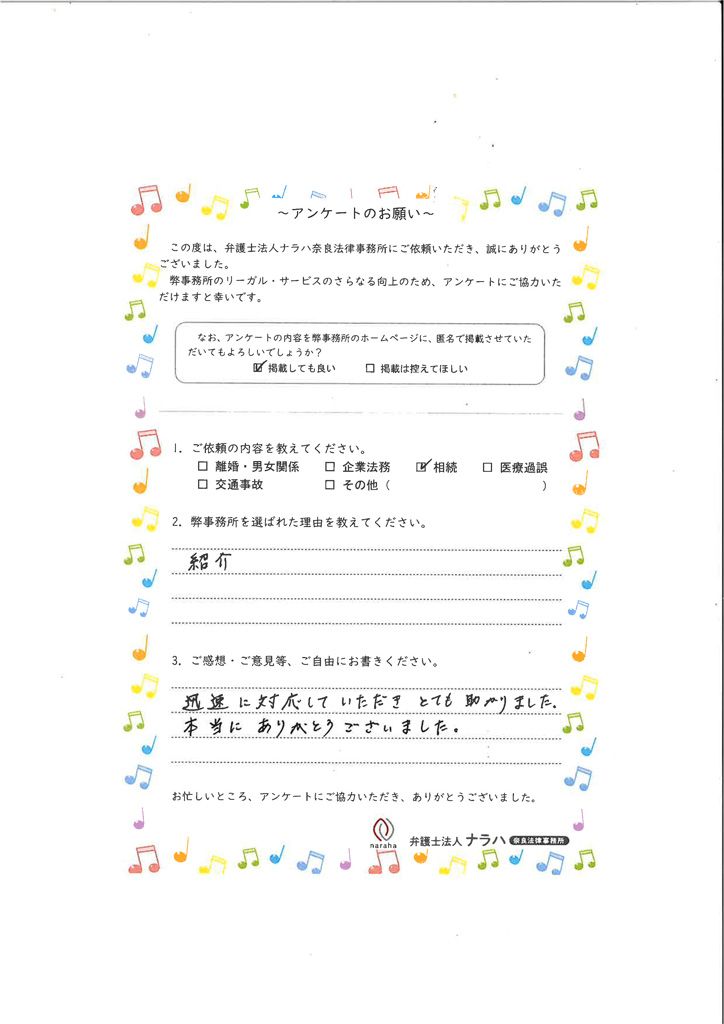

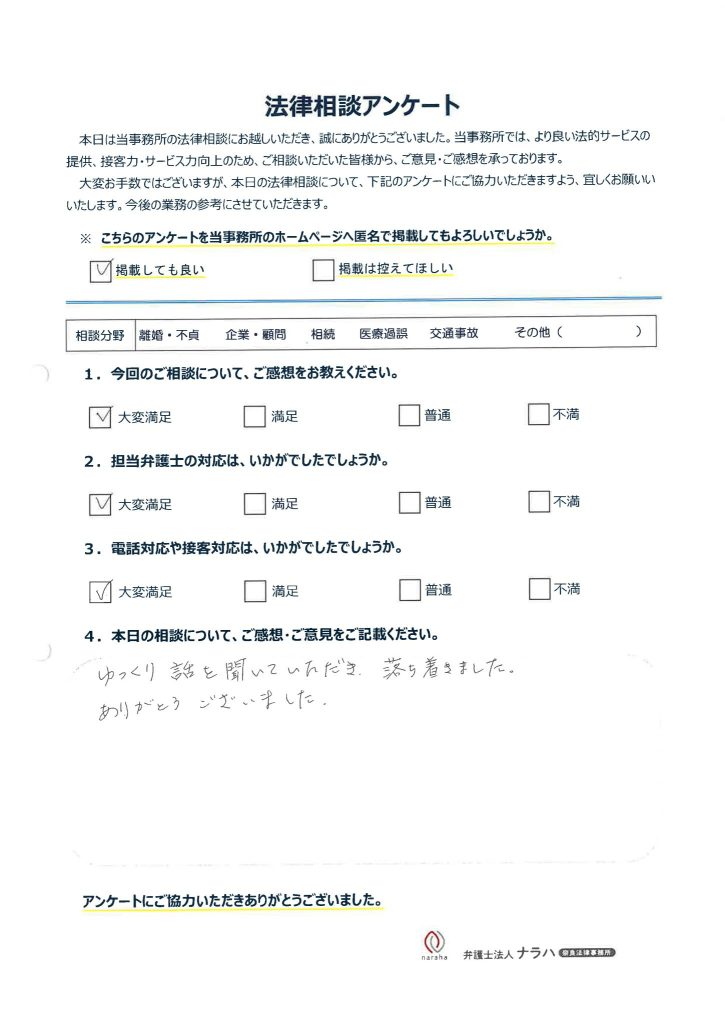
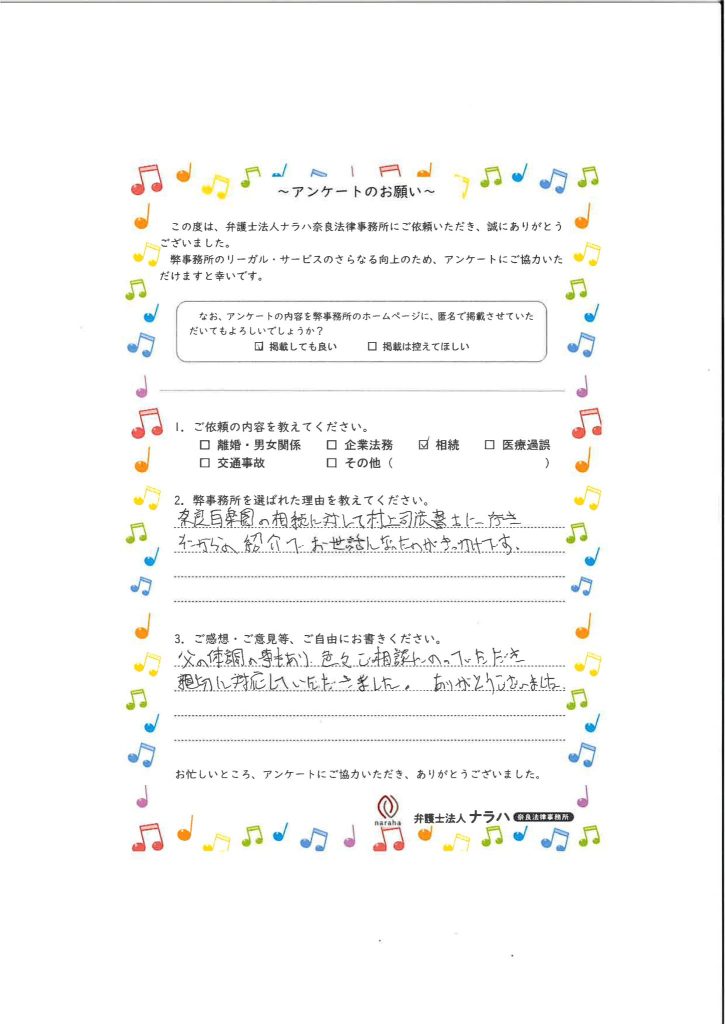
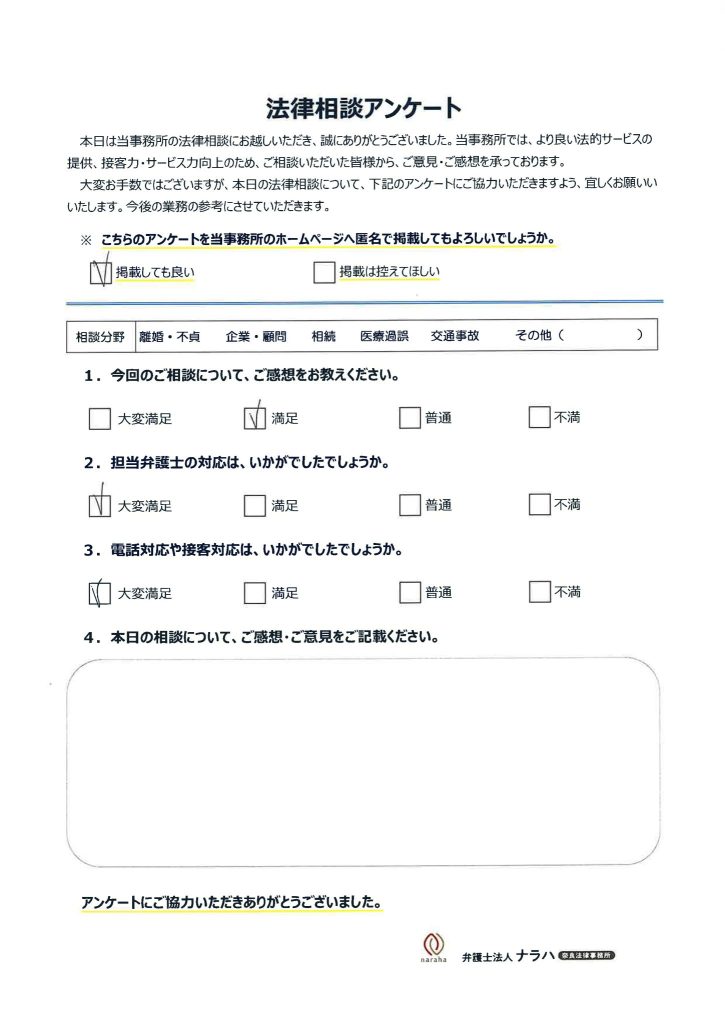
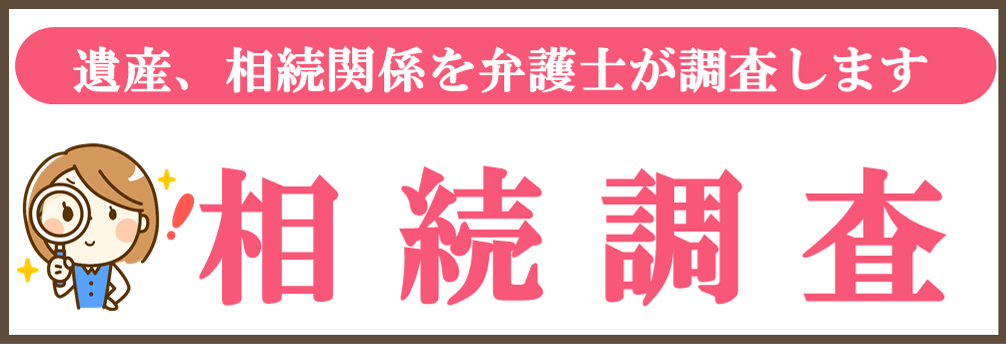

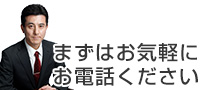

 弁護士法人 ナラハ奈良法律事務所
弁護士法人 ナラハ奈良法律事務所